no">
2014年10月08日
北陸へ 2014 ③日牟礼八幡宮
先回の続き…。
白雲館からすぐの日牟礼八幡宮へ。
八幡川の橋からの景観。元々は豊臣秀次が城下町として整備した時の堀。伝統的建造物群保存地区である。

この写真はグーグルで日牟礼八幡宮を検索するとこれが出てくる。代表的な所なのであろう。
(この写真は筆者が現地で撮影)
近江八幡観光の中心として、多くの人が行き交っている。団体も多い。
ここも10年程前に来た事があったが、余り人で賑わっている様子はなかったし、景観に合わせた土産物屋も少なかった。大分、再開発が為されたのであろう。
日牟礼八幡宮の楼門

古くから近江商人の信仰を集めたことから、規模も大きい。
楼門を抜けて拝殿を望む。

成務天皇の頃、天皇が高穴穂の宮に即位の時、武内宿禰に命じてこの地に琵琶湖の神として大嶋大神を祀ったのが草創とされている。
その後、応神天皇が社の近辺にて休憩した。すると日輪の形を2つ見るという不思議な現象があったので、日群之社八幡宮と名付けられたという。
手水舎


これも寄進のあとでしょうか。

城下町が築かれた八幡であったが、豊臣秀次の失脚に伴い八幡山城は築城から10年足らずで廃城。
以後、東海道と中山道と北国街道が交差する交通の要衝である地の利を生かして商業地として発展、各地へと向かった近江商人たちにより繁栄した。
本殿を参拝


本殿から境内を望む


能舞台

八幡祭りに用いる松明

応神天皇が母である神功皇后の生地・近江国息長(現在の米原市付近)を訪問する途中、大嶋大神を参詣するため琵琶湖から上陸した。その際、湖辺の葦で松明を作り、火を灯して天皇一行を八幡まで道案内したのが、祭の始めと伝えられる。
奉納されている絵馬

白雲館からすぐの日牟礼八幡宮へ。
八幡川の橋からの景観。元々は豊臣秀次が城下町として整備した時の堀。伝統的建造物群保存地区である。

この写真はグーグルで日牟礼八幡宮を検索するとこれが出てくる。代表的な所なのであろう。
(この写真は筆者が現地で撮影)
近江八幡観光の中心として、多くの人が行き交っている。団体も多い。
ここも10年程前に来た事があったが、余り人で賑わっている様子はなかったし、景観に合わせた土産物屋も少なかった。大分、再開発が為されたのであろう。
日牟礼八幡宮の楼門

古くから近江商人の信仰を集めたことから、規模も大きい。
楼門を抜けて拝殿を望む。

成務天皇の頃、天皇が高穴穂の宮に即位の時、武内宿禰に命じてこの地に琵琶湖の神として大嶋大神を祀ったのが草創とされている。
その後、応神天皇が社の近辺にて休憩した。すると日輪の形を2つ見るという不思議な現象があったので、日群之社八幡宮と名付けられたという。
手水舎


これも寄進のあとでしょうか。

城下町が築かれた八幡であったが、豊臣秀次の失脚に伴い八幡山城は築城から10年足らずで廃城。
以後、東海道と中山道と北国街道が交差する交通の要衝である地の利を生かして商業地として発展、各地へと向かった近江商人たちにより繁栄した。
本殿を参拝


本殿から境内を望む


能舞台

八幡祭りに用いる松明

応神天皇が母である神功皇后の生地・近江国息長(現在の米原市付近)を訪問する途中、大嶋大神を参詣するため琵琶湖から上陸した。その際、湖辺の葦で松明を作り、火を灯して天皇一行を八幡まで道案内したのが、祭の始めと伝えられる。
奉納されている絵馬

続く…。
2014年10月07日
本日講演 「主食の民俗 歴史を変えたサツマイモ」 沼津市 Lot.nにて
本日18時半から沼津市のLot.nにて行います。
内容は「主食の民俗 歴史を変えたサツマイモ」です。

(いも地蔵)
数多くある食品の中で、なぜ毎日のように食べ続ける主食という概念があるのだろうか。
日本人は米を主食として来たのだが、地方によってはそれが当てはまらない所もある。
歴史上、何が主食とされて来たのかと、日本の歴史を変えたとも言えるサツマイモの歴史をなぞって行きます。
会費:1000円(ドリンク付き)
時間:18時半から
開催場所はコチラ・沼津市上土町60 岡田ビル1F(元Floyd沼津店 店舗)


※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接お願いします。
 055-919-1060
055-919-1060
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
内容は「主食の民俗 歴史を変えたサツマイモ」です。

(いも地蔵)
数多くある食品の中で、なぜ毎日のように食べ続ける主食という概念があるのだろうか。
日本人は米を主食として来たのだが、地方によってはそれが当てはまらない所もある。
歴史上、何が主食とされて来たのかと、日本の歴史を変えたとも言えるサツマイモの歴史をなぞって行きます。
会費:1000円(ドリンク付き)
時間:18時半から
開催場所はコチラ・沼津市上土町60 岡田ビル1F(元Floyd沼津店 店舗)


※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接お願いします。
 055-919-1060
055-919-1060ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
2014年10月06日
10月5日 散歩かふぇ ちゃらぽこ講演 「人の記憶 地の記憶 火山伝承を読む」 参考文献
10月5日、散歩かふぇ ちゃらぽこにて「人の記憶 地の記憶 火山伝承を読む」についてお話させて頂きました。
お越し下さった皆さん、ありがとうございました。
講座に当たっての参考文献は以下の通りです。
書名/著者
「「富士山の噴火―万葉集から現代まで」/つじよしのぶ」
「天地鳴動-沼津と地震・噴火・津波-/沼津市明治史料館 編」
「富士山噴火とハザードマップ - 宝永噴火の16日間/小山真人」
「富士山宝永大爆発/永原慶二」
「富士山 その自然のすべて /諏訪彰 編」
ご参考にしてください。
なお、宝永噴火後の復興に関しては新田次郎氏の小説『怒る富士』があります。
※次回の散歩かふぇ ちゃらぽこでの講座は11月9日15時から 「二宮金治郎 両道を歩み続けた男」と題し、二宮金治郎の生涯と、二宮が実践した報徳仕法と報徳思想についてお話しします。
お越し下さった皆さん、ありがとうございました。
講座に当たっての参考文献は以下の通りです。
書名/著者
「「富士山の噴火―万葉集から現代まで」/つじよしのぶ」
「天地鳴動-沼津と地震・噴火・津波-/沼津市明治史料館 編」
「富士山噴火とハザードマップ - 宝永噴火の16日間/小山真人」
「富士山宝永大爆発/永原慶二」
「富士山 その自然のすべて /諏訪彰 編」
ご参考にしてください。
なお、宝永噴火後の復興に関しては新田次郎氏の小説『怒る富士』があります。
※次回の散歩かふぇ ちゃらぽこでの講座は11月9日15時から 「二宮金治郎 両道を歩み続けた男」と題し、二宮金治郎の生涯と、二宮が実践した報徳仕法と報徳思想についてお話しします。
2014年10月05日
本日講演 「人の記憶 地の記憶 火山伝承を読む」 散歩かふぇ ちゃらぽこにて
本日10時半より散歩かふぇ ちゃらぽこにて講演致します。
内容は「人の記憶 地の記憶 火山伝承を読む」です。

(宝永噴火の復興を指揮した代官・伊奈忠順)
秀麗なる富士山。その姿からは火を噴くなど考えられないが、古代から中世に掛けては常に火を噴く山であった。
そして宝永の大噴火において、富士山の噴火は社会にどんな影響を与えたのか。
歴史に刻まれた富士山の噴火を体験した人の日記や伝承から、噴火に遭った人の感情や、土地に刻まれた先人たちの思いを掬って行きます。
「富士山・火山・災害史・富士信仰・平安時代・江戸時代」に関心がある方にオススメ。
会費:1500円(ドリンク付き)
時間:15時から
開催場所はコチラ・
※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはちゃらぽこさんへ直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
内容は「人の記憶 地の記憶 火山伝承を読む」です。

(宝永噴火の復興を指揮した代官・伊奈忠順)
秀麗なる富士山。その姿からは火を噴くなど考えられないが、古代から中世に掛けては常に火を噴く山であった。
そして宝永の大噴火において、富士山の噴火は社会にどんな影響を与えたのか。
歴史に刻まれた富士山の噴火を体験した人の日記や伝承から、噴火に遭った人の感情や、土地に刻まれた先人たちの思いを掬って行きます。
「富士山・火山・災害史・富士信仰・平安時代・江戸時代」に関心がある方にオススメ。
会費:1500円(ドリンク付き)
時間:15時から
開催場所はコチラ・
※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはちゃらぽこさんへ直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
2014年10月03日
北陸へ 2014 ②為心町
ブーメラン通りにあった趣ある薬局

ブーメラン通りからやや外れて杜が見えたので、そこへ歩いてみる。
八幡神社 それほど大きい所ではないが、説明版によると応神天皇が創建したという古社である。




今向かっている日牟礼八幡宮からこの八幡神社まで一直線の道路があったという。
再び日牟礼八幡宮へ向かって歩いて10分ほどで為心町通りという所に入る。家並みが趣深い所になっていく。
豊臣政権に仕えた為心斎という者が住んでいた事にちなむ。
赤こんにゃくの乃利松

創業明治24年。
近江八幡では「こんにゃくは赤い物だと思っていた」と言われるほど、地元では古くから親しまれている八幡名物赤こんにゃく。
特徴的な「赤」は三二酸化鉄という食品添加物による着色で鉄分を豊富に含み「鉄骨こんにゃく」とも呼ばれる。
ちょっと何のお店かは分からず

近江八幡教会

1879年、同志社の新島襄らが聖書を講義する「八幡講義所」を創り伝道を行った。
1905年、ヴォ-リズがこの地に近江ミッション(兄弟社)をつくり、1907年に現在の教会を建築した。
電線邪魔だな・・・
松前屋 岡田屋彌三右衛門邸跡

江戸期に松前藩の下請けとして蝦夷地開発に従事した恵比寿屋・岡田彌三右衛門家の邸宅跡。屋号は近江八幡では「松前屋」、松前では「恵比須屋」
初代は、1614年に24歳で北海道松前に渡り、呉服・太物などを商い、後に漁業も手がけた。小樽を中心に漁場を場所請負し、鰊の豊漁で巨利を得た。
五代目の頃には、最大23もの漁場を請け負い、炭坑採掘、農場経営、道路の開削など多方面で活躍した。
十一代目が函館より室蘭に向かう道中で登別の山中で休憩した際に、川筋に湯気が立っているのを発見、これが後の登別温泉につながったと伝えられている。
1918年の北海道開道50年記念事業では、功労者として岡田家に追彰状が送られ、13代目岡田八十次が受領している。
日牟礼八幡宮に面した通りに出る。

日牟礼八幡宮の向かいにある白雲館

1877年に八幡東学校として建てられた擬洋風建築。建設費の六千円は大半が市民の寄付によるものであった。
国の登録有形文化財建造物である。

1994年に解体修理された際に創建時の姿に復元され、以降観光案内所等として活用されている。
現在、1階には近江八幡観光物産協会の事務所が置かれ、観光案内資料や写真展示および絵葉書や特産品の展示販売のスペースとなっている。
階段の所にあったステンドグラス

2階はギャラリー利用のほかイベント開催などにも対応している。

では、日牟礼八幡宮に向かう。
続く…
2014年10月02日
10月7日講演 「主食の民俗 歴史を変えたサツマイモ」 沼津市 Lot.nにて
10月7日18時半から沼津市のLot.nにて行います。
内容は「主食の民俗 歴史を変えたサツマイモ」です。
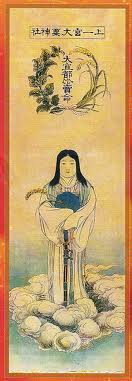
(食物を生み出したオオゲツヒメ)
数多くある食品の中で、なぜ毎日のように食べ続ける主食という概念があるのだろうか。
日本人は米を主食として来たのだが、地方によってはそれが当てはまらない所もある。
歴史上、何が主食とされて来たのかと、日本の歴史を変えたとも言えるサツマイモの歴史をなぞって行きます。
会費:1000円(ドリンク付き)
時間:18時半から
開催場所はコチラ・沼津市上土町60 岡田ビル1F(元Floyd沼津店 店舗)


※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接お願いします。
 055-919-1060
055-919-1060
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
内容は「主食の民俗 歴史を変えたサツマイモ」です。
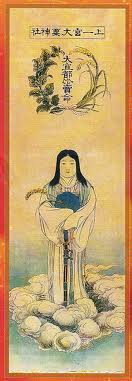
(食物を生み出したオオゲツヒメ)
数多くある食品の中で、なぜ毎日のように食べ続ける主食という概念があるのだろうか。
日本人は米を主食として来たのだが、地方によってはそれが当てはまらない所もある。
歴史上、何が主食とされて来たのかと、日本の歴史を変えたとも言えるサツマイモの歴史をなぞって行きます。
会費:1000円(ドリンク付き)
時間:18時半から
開催場所はコチラ・沼津市上土町60 岡田ビル1F(元Floyd沼津店 店舗)


※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接お願いします。
 055-919-1060
055-919-1060ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
2014年10月01日
富山県射水市・櫛田神社
ある時は信仰の場であり、ある時には教育の場であり、ある時には経済の場である。
神社にはその土地の歴史が詰まっている・・・。
ここでは私が尋ねた神社を紹介します。

櫛田神社は富山県射水市串田6841に座する神社で、延喜式内社で旧社格は県社ある。

創建は社伝には、仲哀天皇の時代に武内宿禰が勧請して創祀したと伝える。
当地に残る伝承では、近くにあった大きな池に大蛇が棲み、村人を食っていたが、あるとき、娘を食ったときに、その娘が髪に挿していた櫛が大蛇の咽につまって大蛇が死んだので、娘と櫛を祀ったのが当社の始まりであると伝える。


祭神は素盞嗚尊・櫛稲田姫命。
他に武内大臣(武内宿禰)・豊臣大臣(豊臣秀吉)・ 源義将君(斯波義将)・大亜利家(前田利家)などの人物神を配祀する。
神紋は、「剣に櫛抱き」。一本の剣を、櫛が抱いた形。

祭神・武素盞嗚尊を、祭神・櫛稻田姫命が抱き包んだ形だろうか。
例大祭は9月10日、火渡り神事が有名である。
扁額は正力松太郎の筆による

手水舎



今までの訪ねた神社をマッピングしました。ご参考にして下さい。
より大きな地図で
神社にはその土地の歴史が詰まっている・・・。
ここでは私が尋ねた神社を紹介します。

櫛田神社は富山県射水市串田6841に座する神社で、延喜式内社で旧社格は県社ある。

創建は社伝には、仲哀天皇の時代に武内宿禰が勧請して創祀したと伝える。
当地に残る伝承では、近くにあった大きな池に大蛇が棲み、村人を食っていたが、あるとき、娘を食ったときに、その娘が髪に挿していた櫛が大蛇の咽につまって大蛇が死んだので、娘と櫛を祀ったのが当社の始まりであると伝える。


祭神は素盞嗚尊・櫛稲田姫命。
他に武内大臣(武内宿禰)・豊臣大臣(豊臣秀吉)・ 源義将君(斯波義将)・大亜利家(前田利家)などの人物神を配祀する。
神紋は、「剣に櫛抱き」。一本の剣を、櫛が抱いた形。

祭神・武素盞嗚尊を、祭神・櫛稻田姫命が抱き包んだ形だろうか。
例大祭は9月10日、火渡り神事が有名である。
扁額は正力松太郎の筆による

手水舎



今までの訪ねた神社をマッピングしました。ご参考にして下さい。
より大きな地図で
2014年10月01日
富山県射水市・櫛田神社








ある時は信仰の場であり、ある時には教育の場であり、ある時には経済の場である。
神社にはその土地の歴史が詰まっている・・・。
ここでは私が尋ねた神社を紹介します。
櫛田神社は富山県射水市串田6841に座する神社で、延喜式内社である。
創建は第十二代景行天皇の御代。
祭神はみこと)。
例大祭は4月5日
今までの訪ねた神社をマッピングしました。ご参考にして下さい。
より大きな地図で




