no">
2016年02月29日
大磯から平塚散歩 ④
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/midori/hike.htm" target="_blank">湘南平から下山する。

その途中にあった看板。
高来神社

ここは以前にも訪れている所である。
しかし、改めて設置している案内板など見ると、現在の高麗山の麓にある里宮から山頂の上宮へと神輿を以って神霊を遷す山神輿についてや、室町時代の関東の戦乱である永享の乱や、後北条氏が狼煙台としたり、後北条氏に対して戦争を仕掛けた上杉謙信によって陣が構えられたりした歴史もある事が解説されていた。

高来神社を後にし、平塚方面へ
途中で境内に横穴があった善福寺を望む。
平塚との境にあった「大磯トラック食堂」気になる…

文房具メーカーのパイロットの工場内にある「蒔絵工房NAMIKI」を見学する。

株式会社パイロットコーポレーションの前身「並木製作所」は1918(大正七)年、東京高等商船学校(現東京海洋大)出身の並木良輔、和田正雄両氏が興し、万年筆の製造販売を始めた。
海外の高級品と勝負するため、万年筆に蒔絵を施すことを発案。漆工芸の草分けである六角紫水氏と、弟子で後に人間国宝となり、「漆の神様」と呼ばれた松田権六氏の指導で完成させた。当時、万年筆の軸に使われていたエボナイトという樹脂は日光が当たると劣化してしまうため、漆で保護するという意味合いもあった。
1925(大正十四)年、並木、和田の両氏は、販路開拓の為に蒔絵万年筆を携えて欧米を訪問。好評を得て、帰国後、ロンドンから最初の注文が入る。
その翌年、1926(大正十五)年に松田権六氏を中心に蒔絵万年筆を研究、創作する蒔絵製作集団「國光會(こっこうかい)」を結成。
1930(昭和五)年には英国のダンヒル社と契約し、「ダンヒル・ナミキ万年筆」としてロンドンやパリ、ニューヨークなどで売りに出され、同年のロンドン海軍軍縮会議で調印に使われた。
平塚事業所は敗戦後の1948(昭和二十三)年、旧海軍第二火薬廠跡地の払い下げを受けて開設された。資料館として使われるようになった通称「レンガ棟」は大正後期に建てられており、2001年に平塚事業所にあった筆記具資料館を閉じて地元で惜しまれていたこと、平塚市に「平塚の近代史を伝え残してほしい」と望まれたことから、「蒔絵工房 NAMIKI」として開設し、約100点の漆芸品を中心に展示している。展示されているのは、大正期のもの、寺井直次氏や田口善国氏ら「人間国宝」の作品、「技術の継承」のために職人が構想から三年かけて完成させたものなど。
現在は平塚事業所にいる蒔絵師三人に加え、石川県輪島市などの職人が協力して伝統工芸である蒔絵技術を受け継いでいる。
見てると漆の文字通り「漆黒」の空間に、蒔絵や螺鈿の星々が輝いているかのようである。ただ、正直な所、外国人が好みそうな和柄、という感じで、実際、購入するのは外国人、主にフランスなどが多いそうだ。
下世話な話だが、展示されている品はどれもが二ケタ万円を超える。良い物である事は分かるのだが、持っていても浮いてしまいそうである。
しかし、一般に「伝統」と呼ばれている物も、常に需要と供給が為された上でないと続かない。技術の伝承としては最も良い形と言える。
直近では、朝の連続テレビドラマ「まれ」にて蒔絵職人が取り上げられたところから、見学に来られる方も多いという。
この界隈は工場が多い。

それも元は軍需工場の跡である。それ以前は江戸幕府の直轄地で、中原御林という。徳川家康が鷹狩の際に仮の御殿を築き、見渡されるのを防止するために林を設けたという。

軍需工場があった故、空襲も受けてしまったという一面がある。
続く…
2016年02月27日
3月12日講演 「人の記憶 地の記憶 地震伝承を読む」 静岡市 くればにて
3月12日14時より静岡市のシニアライフ支援センター「くれば」にて講演致します。
内容は「人の記憶 地の記憶 地震伝承を読む」です。
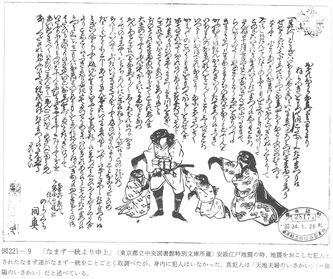
日本列島に住んでいる限り、一生のうちに一度は巨大地震に遭遇すると言われている。
しかし、度重なる学者の警告にも関わらず「地震なんて来なければわからない」という認識が大抵である。それは想定される被害が単なる数字だからではないだろうか。
今回は歴史に刻まれた巨大地震を体験した人の日記や伝承から、巨大地震に遭った人の感情や、土地に刻まれた先人たちの思いを掬って行きます。
「歴史地震・東海地震・災害史・民俗学」
などに関心がある方にオススメです。
会費:500円
開催場所はコチラ・静岡市両替町2丁目3-6大原ビル1F シニアライフ支援センター「くれば」
参加は自由です。直接、来場してください。問い合わせはコチラから。054(252)8018
もしくはオーナーメールで直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました
内容は「人の記憶 地の記憶 地震伝承を読む」です。
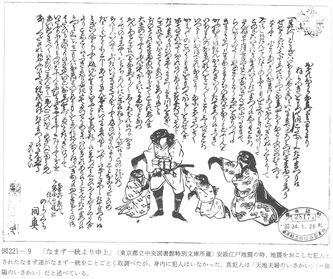
日本列島に住んでいる限り、一生のうちに一度は巨大地震に遭遇すると言われている。
しかし、度重なる学者の警告にも関わらず「地震なんて来なければわからない」という認識が大抵である。それは想定される被害が単なる数字だからではないだろうか。
今回は歴史に刻まれた巨大地震を体験した人の日記や伝承から、巨大地震に遭った人の感情や、土地に刻まれた先人たちの思いを掬って行きます。
「歴史地震・東海地震・災害史・民俗学」
などに関心がある方にオススメです。
会費:500円
開催場所はコチラ・静岡市両替町2丁目3-6大原ビル1F シニアライフ支援センター「くれば」
参加は自由です。直接、来場してください。問い合わせはコチラから。054(252)8018
もしくはオーナーメールで直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました
2016年02月26日
【28日】沼津市・御幸町遺跡発掘現場説明会
今月28日午前10時より、沼津市民文化センター隣の香陵グランド(遺跡名・御幸町遺跡)にて行われている埋蔵文化財発掘調査の現場説明会が行われます。

沼津市民文化センターの建設時に行われた発掘調査では、弥生時代の住居跡が数多く発見されたため、隣接する香陵グランドでも弥生時代の土器が多数、住居跡や方形周溝墓などが発見されました。
なお、旧制沼津中学が所在していた所でもあるので、沼津中学名残の水路跡なども確認されています。
■2016年2月28日午前10時より。(午前中のみです)
■現地には駐車場がありませんので、自動車での来場は近隣の有料駐車場をご利用ください。
●徒歩 沼津駅南口より15分程度
●バス 沼津駅南口より(乗車約6~7分)
・ 沼津登山東海バス(4番のりば)『外原行き』利用、「文化センター①」下車
・ 沼津登山東海バス(6番のりば)利用、「文化センター北②」下車
・ 伊豆箱根バス(7番のりば)利用、「市役所前③」又は「裁判所前④」下車
※4番 沼津登山東海バスは外原(温水プール)行きのみ
■問い合わせは沼津市文化振興課・文化財センターへ。

沼津市民文化センターの建設時に行われた発掘調査では、弥生時代の住居跡が数多く発見されたため、隣接する香陵グランドでも弥生時代の土器が多数、住居跡や方形周溝墓などが発見されました。
なお、旧制沼津中学が所在していた所でもあるので、沼津中学名残の水路跡なども確認されています。
■2016年2月28日午前10時より。(午前中のみです)
■現地には駐車場がありませんので、自動車での来場は近隣の有料駐車場をご利用ください。
●徒歩 沼津駅南口より15分程度
●バス 沼津駅南口より(乗車約6~7分)
・ 沼津登山東海バス(4番のりば)『外原行き』利用、「文化センター①」下車
・ 沼津登山東海バス(6番のりば)利用、「文化センター北②」下車
・ 伊豆箱根バス(7番のりば)利用、「市役所前③」又は「裁判所前④」下車
※4番 沼津登山東海バスは外原(温水プール)行きのみ
■問い合わせは沼津市文化振興課・文化財センターへ。
2016年02月25日
2月24日講演 「幕府流転 天下相食む下剋上」について参考文献
2月24日、沼津市の高嶋酒造にて「幕府流転 天下相食む下剋上」についてお話させて頂きました。
お越し下さった皆さん、ありがとうございました。
講座に当たっての参考文献は以下の通りです。
書名/著者
「戦国期室町幕府と将軍/山田康弘」
「戦国三好一族/今谷明」
「関東戦国史(全)/千野原靖方」
「続中世東国の支配構造/佐藤博信 」
「戦争の日本史11 畿内・近国の戦国合戦/福島克彦」
「織田信長合戦全録 - 桶狭間から本能寺まで/谷口克広 」
※次回の高嶋酒造での講座は3月30日18時半~、「人の記憶 地の記憶 地震伝承を読む」と題し、過去の巨大地震を記録した日記や歴史的影響について歴史の観点からお話しします。
お越し下さった皆さん、ありがとうございました。
講座に当たっての参考文献は以下の通りです。
書名/著者
「戦国期室町幕府と将軍/山田康弘」
「戦国三好一族/今谷明」
「関東戦国史(全)/千野原靖方」
「続中世東国の支配構造/佐藤博信 」
「戦争の日本史11 畿内・近国の戦国合戦/福島克彦」
「織田信長合戦全録 - 桶狭間から本能寺まで/谷口克広 」
ご参考にして下さい。
※次回の高嶋酒造での講座は3月30日18時半~、「人の記憶 地の記憶 地震伝承を読む」と題し、過去の巨大地震を記録した日記や歴史的影響について歴史の観点からお話しします。
2016年02月24日
本日講演 「幕府流転 天下相食む下剋上」 沼津市 高嶋酒造にて
本日18時半より講演致します。
内容は「幕府流転 天下相食む下剋上」です。

(足利将軍を凌ぐ権力を手にした三好長慶)
室町時代末期、足利将軍の権威は失墜し、将軍ですらそれまでの部下に幕府を追い出される有様であった。それでも力を取り戻そうと、策を巡らし自ら戦場に赴く者も居た。
華々しい戦国大名の活躍の陰で衰退しつつも、戦国時代の鍵を握っていた足利将軍の末期と、「天下人」と呼ばれる者たちの動向を語ります。
「室町時代後期・下剋上・戦国時代・足利将軍・天下人に関心がある方におすすめ。」
参加費:700円。
開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて
※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)
※自由参加ですが、問い合わせ等は高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
内容は「幕府流転 天下相食む下剋上」です。

(足利将軍を凌ぐ権力を手にした三好長慶)
室町時代末期、足利将軍の権威は失墜し、将軍ですらそれまでの部下に幕府を追い出される有様であった。それでも力を取り戻そうと、策を巡らし自ら戦場に赴く者も居た。
華々しい戦国大名の活躍の陰で衰退しつつも、戦国時代の鍵を握っていた足利将軍の末期と、「天下人」と呼ばれる者たちの動向を語ります。
「室町時代後期・下剋上・戦国時代・足利将軍・天下人に関心がある方におすすめ。」
参加費:700円。
開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて
※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)
※自由参加ですが、問い合わせ等は高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
2016年02月23日
大磯から平塚散歩 ③湘南平
楊谷寺横穴群を過ぎて、そのまま高麗山を登ると湘南平に出る。

電波塔が立っている。

ここまでは予想の内だったのだが、自動車道が通じている気軽に来られる所とは思わなかった・・・。

足で登ってきた所に自動車で来た人が闊歩しているのを見ると非常にガックリする。
展望台から北側を望む。曇りの中に丹沢山地。

西側を望む。伊豆半島方面。

南側を望む。先程の沢田美喜記念館も見えますね。

東側を望む。

実はこれだけの平たい面があるのは、大戦中に高射砲の砲台が設けられたからの様だ。
隣接する平塚には火薬廠があったことを考えると、真っ先に爆撃の対象にされるだろう。その防御もあった。
だが、昭和20年7月16日夜の平塚大空襲時には応射がなかったという。これは既に爆撃によって停電し、機能が沈黙していたからとの事。
戦後暫くは荒廃したままであったが、昭和32年に平塚市と神奈川中央交通がこの地を自然公園とする計画を立てて開発・整備し、当時の市長である戸川貞雄が湘南平と命名した。
電波受信している様子なんですがなんだったのか。

続く…
2016年02月22日
3月5日講演 「日本再起動 室町ルネサンス」 三島市 カフェうーるーにて
3月5日9時半から三島市のカフェうーるーにて行います。
内容は「日本再起動 室町ルネサンス」です。

室町三代将軍・足利義満が亡くなると、その強大な権力の喪失はあらゆる矛盾を噴出させ、幕府は急速に衰えていく。幕府は権威を取り戻そうと足掻く一方で、その権威に頼らず新たな時代を切り拓こうとしていた者たちが居た。
室町時代中期における経緯と、その中で生まれた今の日本に通じる文化についてお話しします。
「室町時代・下剋上・社会学・一揆・戦国時代に関心がある方におすすめ。」
会費:500円+ワンドリンクオーダー
時間:9時半から11時半予定
開催場所はコチラ・カフェうーるー(三島市南本町13-30 ☎055-981-5539)
参加の申し込み不要。
問い合わせはオーナーメール、もしくはうーるーさんへお願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
内容は「日本再起動 室町ルネサンス」です。

室町三代将軍・足利義満が亡くなると、その強大な権力の喪失はあらゆる矛盾を噴出させ、幕府は急速に衰えていく。幕府は権威を取り戻そうと足掻く一方で、その権威に頼らず新たな時代を切り拓こうとしていた者たちが居た。
室町時代中期における経緯と、その中で生まれた今の日本に通じる文化についてお話しします。
「室町時代・下剋上・社会学・一揆・戦国時代に関心がある方におすすめ。」
会費:500円+ワンドリンクオーダー
時間:9時半から11時半予定
開催場所はコチラ・カフェうーるー(三島市南本町13-30 ☎055-981-5539)
参加の申し込み不要。
問い合わせはオーナーメール、もしくはうーるーさんへお願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
2016年02月21日
大磯から平塚散歩 ②海から来た人々
沢田美喜記念館を出て、大磯の海岸方面へ向かう。
沢田美喜記念館脇にある大磯迎賓館。

現在はイタリアンレストランであるが、築100年超の洋館。
大正元年(1912)に貿易商・木下健平が、米国帰りの建築家に依頼して建てたもの。メンテナンスの難しさなどから解体の危機などにも見舞われましたが、現存する日本最古の2×4(ツーバイフォー)工法の洋館である事などから、2012年に国登録有形文化財に指定された。
延台寺

曽我兄弟の兄・十郎祐成と結ばれた虎御前が開いた寺。
標柱にある「虎御石」とは、曽我兄弟の仇討ちの相手・工藤祐経が大磯の山下長者の屋敷に度々来ることを知り、刺客を差し向けた。刺客は十郎めがけて矢を射かけたが、矢は見事にはね返され、続いて太刀で切りつけたが歯がたたなかった。良く見ればそれは大きな石であり、刺客は驚いて逃げ去った。
その大きな石が「虎御石」であり、矢の当った辺りに矢傷の窪みができ、長い刀傷もついていた。それ以降、「虎御石」を「十郎の身代わり石」とも呼ぶようになった。
関西感が出ている。

大磯は海のイメージが判然としてあるが、実際の所、間近で見た事はなかった。

宿場の様子や、高級住宅といった一面もあるが、海に面した暮らしというものも本来の姿だろう。

http://www.oisokou.com/" target="_blank">めしや大磯港にて昼食
人気があるのか、何人か並んだ。メニューによっては売り切れも。
私は大ぶりの塩鯖定食を頂いたが満足。
食事後、再び大磯駅方面へ戻って、高麗山の中にある楊谷寺横穴墓を目指して歩く。
大磯町には古代人の墓地である横穴墓群が点在しており、近年の所在調査と埋没している横穴墓を考慮すると1200基に近い数が想定されている。確か、以前歩いた時にも寺の境内にあった横穴を見た事がある。
山中であるが、ウォーキングコースになっているからか、人は時折歩いており、所々で横穴について聞きながら向かう。
楊谷寺横穴墓

楊谷寺横穴群は高麗山の西側にある楊谷寺谷戸一帯に位置し、7世紀初頭の年代を示す土師器や須恵器の長頚瓶などが出土していることから、7世紀前半以降の墓・原始・古代の遺跡として県の重要文化財に指定されている。

此処だけでも、昭和30年代には27基が、平成の調査では21基が確認されている。

天井が屋根型になっている家形横穴墓、 切妻造家形、アーチ型などがあり、通常の横穴の脇に側室を設けた棺室横穴墓などがあり、横穴墓の形態変遷の指標になり得る史跡の一つと言えます。

高麗山は高句麗系渡来人の居住した地域とも推定され、近隣の釜口古墳は朝鮮式の横穴式石室を持っていることから、高句麗系渡来人の墓とも考えられます。


高麗山は古くから聖なる山として認識されていたが、その一角の谷には人の霊魂が鎮まる場としてあった訳だ。
続く…
2016年02月19日
3月1日講演 「人の記憶 地の記憶 地震伝承を読む」 沼津市 Lot.nにて
3月1日18時半から沼津市のLot.nにて行います。
内容は「人の記憶 地の記憶 地震伝承を読む」です。
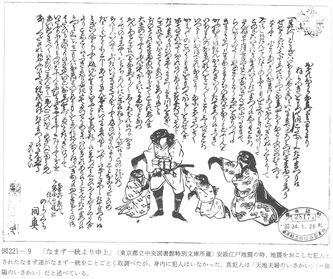
日本列島に住んでいる限り、一生のうちに一度は巨大地震に遭遇すると言われている。
しかし、度重なる学者の警告にも関わらず「地震なんて来なければわからない」という認識が大抵である。それは想定される被害が単なる数字だからではないだろうか。
今回は歴史に刻まれた巨大地震を体験した人の日記や伝承から、巨大地震に遭った人の感情や、土地に刻まれた先人たちの思いを掬って行きます。
「歴史地震・東海地震・災害史・民俗学」
などに関心がある方にオススメです。
会費:1000円(ドリンク付き)
時間:18時半から
開催場所はコチラ・沼津市上土町10 (それまでの店舗の道向かいです
)
※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
参加は自由です。Lot.nさんへ直接来場ください。
変更や中止の問い合わせ、申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへお問い合わせください
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
内容は「人の記憶 地の記憶 地震伝承を読む」です。
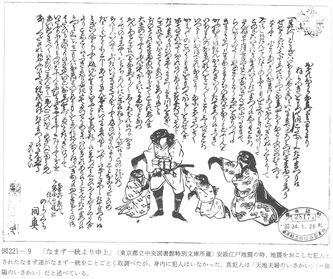
日本列島に住んでいる限り、一生のうちに一度は巨大地震に遭遇すると言われている。
しかし、度重なる学者の警告にも関わらず「地震なんて来なければわからない」という認識が大抵である。それは想定される被害が単なる数字だからではないだろうか。
今回は歴史に刻まれた巨大地震を体験した人の日記や伝承から、巨大地震に遭った人の感情や、土地に刻まれた先人たちの思いを掬って行きます。
「歴史地震・東海地震・災害史・民俗学」
などに関心がある方にオススメです。
会費:1000円(ドリンク付き)
時間:18時半から
開催場所はコチラ・沼津市上土町10 (それまでの店舗の道向かいです
)
※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
参加は自由です。Lot.nさんへ直接来場ください。
変更や中止の問い合わせ、申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへお問い合わせください
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
2016年02月18日
大磯から平塚散歩 ①澤田美喜記念館
友人に誘われて、大磯から平塚の気になる場所を巡る散歩をしました。
まずは大磯駅前にある澤田美喜記念館に入ります。

実は以前に散歩かふぇ ちゃらぽこさんの東海道ウォークの企画で、今回と逆の平塚から大磯に歩いた際、大磯は終着点だったので、もう閉館時間となっていたので気になっていた。
澤田美喜女史のレリーフ

私はここを開設した澤田美喜女史が岩崎彌太郎の孫であるという点と、女史が蒐集した隠れキリシタンについての展示がある、という所で気になっていたが、友人は人類学の観点からこの施設で行われた日米混血児の体格を20年に亘って長期観察研究が気になっていたそうだ。
敷地に入った時間は開館時間よりやや早かったため、掃除をしていた職員の方が施設について色々とお話ししてくれた。

第二次世界大戦後、日本に進駐したアメリカ軍兵士を中心とした連合国軍兵士と日本人女性の間に強姦や売春、あるいは自由恋愛の結果生まれたものの、見捨てられてしまった二十万人と言われた子供たちの存在を日本占領の恥部と考えた日米両政府とも、この問題には敢えて触れたがらなかった。
各地で見聞される捨て子や間引きの状況に心を痛めた澤田美喜女史は、三菱財閥が財産税として物納されていた岩崎家大磯別邸を、混血孤児のための施設として400万円で買い戻して昭和23年2月1日に設立した。
ホーム設立後に最初の寄付をしてくれた、三井家で働いていた英国人家庭教師エリザベス・サンダースにちなみ、「エリザベス・サンダース・ホーム」と名付け、孤児の養育、教育、職業訓練などのために後半生を捧げた。
女史は「たとえ一瞬でも、汝がその子の母となれば、日本中にいる彼のごとき境遇の多数の子供たちのために、汝が母親代りになるべし」と述べている。そこには「信仰半分、意地半分」という精神である。
澤田美喜記念館

昭和63年4月19日に澤田美喜記念館として開設。1階が展示室と受付、2階に礼拝堂といった構成である。

沢田美喜は隠れキリシタンの遺物の収集家でもあった。生前に美喜が蒐集した世界各国の十字架や、日本全国から集められた貴重な資料851点のうち、370点あまりが同館に展示されている。

内部は撮影できないので写真は無いが、板彫り踏絵、背部にマリア像を彫ったマリア観音像、キリシタン禁止令の高札、鏡面に光を当てるとキリスト像が照らし出される「魔鏡」、日本最初のキリシタン大名・大村純忠の領地であった「横瀬浦天主堂の鐘」など、同様の博物館では群を抜くコレクションを保有している。
私も各地のキリシタンの歴史を伝える資料館はいくつか巡っているが、確かにコレクションは素晴らしい。ただ、あくまで個人のコレクションであって、歴史を伝えるような展示では無かったと個人的には思う。

アメリカでも、日米混血孤児たちの話を聞いて深い同情を示し、引き取って世話をしたいと申し出るものも多くあった。美喜は米国でも人種差別が強いことをよく知っていたが、それでも孤児たちには米国で育ったほうが日本で育つよりも、明るい未来が開かれていると信じていた。
更にブラジルへの開拓民として卒業生を送り込もうと計画し、「アマゾン教室」と名付けた実習室を設け、卒業生を現地の「聖ステパノ農場」に送った。ブラジルが世界で混血に対して最も寛容な国の一つであったと考えていたのだろう。
だが、ブラジル政府の黒人移民不歓迎政策があり成功とは言えなかったが、1968年に教え子の1人が移民で成功している。
個人的には移民史を講座にもしているが、戦後移民のある一面を知れた。
「ジョセフィーンの家」とある。

ジョセフィーンとは、アメリカ出身でパリで活躍したダンサーであるジョセフィン・ベーカー。ベーカーがパリで活動していた時にパリに赴任していた外交官の夫・廉三と共に沢田美喜と友人になった。
パリで成功した彼女であったが、アメリカでの黒人に対する差別は変らなかった。ニューヨークでの公演時に、ベーカーを泊めるホテルが悉く差別心から拒否した。その際、沢田美喜は自分の部屋に泊めたという。
この恩返しにと、エリザベス・サンダース・ホームのための募金コンサートを日本国内で企画し、1954年の春に来日した。ジョセフィンは、3週間の日本滞在期間に22回の公演を行い、集められたお金は全部ホームに寄付した。
ベーカーもまた、様々な人種の12人の孤児を養子とし、人種差別に立ち向かった女性だった。
聖ステパノ学園小学校・中学校の建物の一部


孤児院出身の子どもたちが、小学校、中学校に上がる年齢になり、周囲の「混血児」への偏見迫害や、学校生活との折り合いの問題などへの対応から、ホームの中に小学校・中学校も設立した。
小学校は、1953年に創立され、美喜の三男・晃の洗礼名から、聖ステパノ学園小学校と命名された。中学校は1959年に併設された。
なお、美喜の三男・晃は1945年1月12日、インドシナ沖で日本の巡洋艦「樫」と共に海底に沈んだ。19歳だった。
夫の澤田廉三氏は戦前から外交官として活動し、戦後は日本の国連加盟に尽力した。
ホームの子供たちは親に捨てられたという事と、肌の色が違うということで世間から二重の不当な差別を受けていた。そのため、ホームのある大磯の海岸で海水浴を楽しむことさえもできず、廉三の故郷である鳥取県岩美町の海岸でやっと受け入れて貰えた。ここはホームの第二の故郷であり、澤田夫妻の墓もここにある。
現在でも親の虐待、育児放棄、あまりの夫婦喧嘩による精神的外傷など様々な心の傷を負った子供たちが共同生活をしている。定員百人のところ、現在は八十人ほどいるとの事。
エリザベス・サンダース・ホームへと繋がるトンネル

このトンネルは元々岩崎家の別荘であった時から存在するが、子供たちが暮らしていた施設と隔絶していた世間とを繋ぐ一本の暗い通り道を示しているかに思えた。
ここで同行者の方が
「ここもそうだけど、アメリカ軍の日本占領下やベトナムでは現地の女性と兵士の子供の問題があるのだけど、慰安婦ではその面は無いのだけど。」
うーん、その視点は鋭いなぁと思って、足を進めた。
まずは大磯駅前にある澤田美喜記念館に入ります。

実は以前に散歩かふぇ ちゃらぽこさんの東海道ウォークの企画で、今回と逆の平塚から大磯に歩いた際、大磯は終着点だったので、もう閉館時間となっていたので気になっていた。
澤田美喜女史のレリーフ

私はここを開設した澤田美喜女史が岩崎彌太郎の孫であるという点と、女史が蒐集した隠れキリシタンについての展示がある、という所で気になっていたが、友人は人類学の観点からこの施設で行われた日米混血児の体格を20年に亘って長期観察研究が気になっていたそうだ。
敷地に入った時間は開館時間よりやや早かったため、掃除をしていた職員の方が施設について色々とお話ししてくれた。

第二次世界大戦後、日本に進駐したアメリカ軍兵士を中心とした連合国軍兵士と日本人女性の間に強姦や売春、あるいは自由恋愛の結果生まれたものの、見捨てられてしまった二十万人と言われた子供たちの存在を日本占領の恥部と考えた日米両政府とも、この問題には敢えて触れたがらなかった。
各地で見聞される捨て子や間引きの状況に心を痛めた澤田美喜女史は、三菱財閥が財産税として物納されていた岩崎家大磯別邸を、混血孤児のための施設として400万円で買い戻して昭和23年2月1日に設立した。
ホーム設立後に最初の寄付をしてくれた、三井家で働いていた英国人家庭教師エリザベス・サンダースにちなみ、「エリザベス・サンダース・ホーム」と名付け、孤児の養育、教育、職業訓練などのために後半生を捧げた。
女史は「たとえ一瞬でも、汝がその子の母となれば、日本中にいる彼のごとき境遇の多数の子供たちのために、汝が母親代りになるべし」と述べている。そこには「信仰半分、意地半分」という精神である。
澤田美喜記念館

昭和63年4月19日に澤田美喜記念館として開設。1階が展示室と受付、2階に礼拝堂といった構成である。

沢田美喜は隠れキリシタンの遺物の収集家でもあった。生前に美喜が蒐集した世界各国の十字架や、日本全国から集められた貴重な資料851点のうち、370点あまりが同館に展示されている。

内部は撮影できないので写真は無いが、板彫り踏絵、背部にマリア像を彫ったマリア観音像、キリシタン禁止令の高札、鏡面に光を当てるとキリスト像が照らし出される「魔鏡」、日本最初のキリシタン大名・大村純忠の領地であった「横瀬浦天主堂の鐘」など、同様の博物館では群を抜くコレクションを保有している。
私も各地のキリシタンの歴史を伝える資料館はいくつか巡っているが、確かにコレクションは素晴らしい。ただ、あくまで個人のコレクションであって、歴史を伝えるような展示では無かったと個人的には思う。

アメリカでも、日米混血孤児たちの話を聞いて深い同情を示し、引き取って世話をしたいと申し出るものも多くあった。美喜は米国でも人種差別が強いことをよく知っていたが、それでも孤児たちには米国で育ったほうが日本で育つよりも、明るい未来が開かれていると信じていた。
更にブラジルへの開拓民として卒業生を送り込もうと計画し、「アマゾン教室」と名付けた実習室を設け、卒業生を現地の「聖ステパノ農場」に送った。ブラジルが世界で混血に対して最も寛容な国の一つであったと考えていたのだろう。
だが、ブラジル政府の黒人移民不歓迎政策があり成功とは言えなかったが、1968年に教え子の1人が移民で成功している。
個人的には移民史を講座にもしているが、戦後移民のある一面を知れた。
「ジョセフィーンの家」とある。

ジョセフィーンとは、アメリカ出身でパリで活躍したダンサーであるジョセフィン・ベーカー。ベーカーがパリで活動していた時にパリに赴任していた外交官の夫・廉三と共に沢田美喜と友人になった。
パリで成功した彼女であったが、アメリカでの黒人に対する差別は変らなかった。ニューヨークでの公演時に、ベーカーを泊めるホテルが悉く差別心から拒否した。その際、沢田美喜は自分の部屋に泊めたという。
この恩返しにと、エリザベス・サンダース・ホームのための募金コンサートを日本国内で企画し、1954年の春に来日した。ジョセフィンは、3週間の日本滞在期間に22回の公演を行い、集められたお金は全部ホームに寄付した。
ベーカーもまた、様々な人種の12人の孤児を養子とし、人種差別に立ち向かった女性だった。
聖ステパノ学園小学校・中学校の建物の一部


孤児院出身の子どもたちが、小学校、中学校に上がる年齢になり、周囲の「混血児」への偏見迫害や、学校生活との折り合いの問題などへの対応から、ホームの中に小学校・中学校も設立した。
小学校は、1953年に創立され、美喜の三男・晃の洗礼名から、聖ステパノ学園小学校と命名された。中学校は1959年に併設された。
なお、美喜の三男・晃は1945年1月12日、インドシナ沖で日本の巡洋艦「樫」と共に海底に沈んだ。19歳だった。
夫の澤田廉三氏は戦前から外交官として活動し、戦後は日本の国連加盟に尽力した。
ホームの子供たちは親に捨てられたという事と、肌の色が違うということで世間から二重の不当な差別を受けていた。そのため、ホームのある大磯の海岸で海水浴を楽しむことさえもできず、廉三の故郷である鳥取県岩美町の海岸でやっと受け入れて貰えた。ここはホームの第二の故郷であり、澤田夫妻の墓もここにある。
現在でも親の虐待、育児放棄、あまりの夫婦喧嘩による精神的外傷など様々な心の傷を負った子供たちが共同生活をしている。定員百人のところ、現在は八十人ほどいるとの事。
エリザベス・サンダース・ホームへと繋がるトンネル

このトンネルは元々岩崎家の別荘であった時から存在するが、子供たちが暮らしていた施設と隔絶していた世間とを繋ぐ一本の暗い通り道を示しているかに思えた。
ここで同行者の方が
「ここもそうだけど、アメリカ軍の日本占領下やベトナムでは現地の女性と兵士の子供の問題があるのだけど、慰安婦ではその面は無いのだけど。」
うーん、その視点は鋭いなぁと思って、足を進めた。
続く…
2016年02月17日
2月14日ちゃらぽこ講演 「海越え、果つる地まで ~雄飛と絶望の移民史~」について参考文献
2月14日、散歩かふぇ ちゃらぽこにて「海越え、果つる地まで 雄飛と絶望の移民史」についてお話させて頂きました。
お越し下さった皆さん、ありがとうございました。
講座に当たっての参考文献は以下の通りです。
書名/著者
「アメリカに生きた日本人移民: 日系一世の光と影/村山裕三」
「日本人移民: ハワイ, 北米大陸/藤崎康夫, 山本耕二 」
「サンダカン八番娼館/山崎朋子 」
「静岡県と満州開拓団/櫻井規順」
「ブラジルへ: 日本人移民物語/藤崎康夫 」
ご参考にしてください。
※次回の散歩かふぇ ちゃらぽこでの講座は、3月13日15時から「天野芳太郎 太平洋を越える不死鳥」と題し、中南米で活躍した実業家・天野芳太郎の生涯についてお話します。
お越し下さった皆さん、ありがとうございました。
講座に当たっての参考文献は以下の通りです。
書名/著者
「アメリカに生きた日本人移民: 日系一世の光と影/村山裕三」
「日本人移民: ハワイ, 北米大陸/藤崎康夫, 山本耕二 」
「サンダカン八番娼館/山崎朋子 」
「静岡県と満州開拓団/櫻井規順」
「ブラジルへ: 日本人移民物語/藤崎康夫 」
ご参考にしてください。
※次回の散歩かふぇ ちゃらぽこでの講座は、3月13日15時から「天野芳太郎 太平洋を越える不死鳥」と題し、中南米で活躍した実業家・天野芳太郎の生涯についてお話します。
2016年02月16日
2月13日講演 「幕府流転 天下相食む下剋上」について参考文献
2月13日、静岡市のくればにて「幕府流転 天下相食む下剋上」についてお話させて頂きました。
お越し下さった皆さん、ありがとうございました。
講座に当たっての参考文献は以下の通りです。
書名/著者
「戦国期室町幕府と将軍/山田康弘」
「戦国三好一族/今谷明」
「関東戦国史(全)/千野原靖方」
「続中世東国の支配構造/佐藤博信 」
「戦争の日本史11 畿内・近国の戦国合戦/福島克彦」
「織田信長合戦全録 - 桶狭間から本能寺まで/谷口克広 」
※次回のくればでの講座は3月12日14時~、「人の記憶 地の記憶 地震伝承を読む」と題し、過去の巨大地震を記録した日記や歴史的影響について歴史の観点からお話しします。
お越し下さった皆さん、ありがとうございました。
講座に当たっての参考文献は以下の通りです。
書名/著者
「戦国期室町幕府と将軍/山田康弘」
「戦国三好一族/今谷明」
「関東戦国史(全)/千野原靖方」
「続中世東国の支配構造/佐藤博信 」
「戦争の日本史11 畿内・近国の戦国合戦/福島克彦」
「織田信長合戦全録 - 桶狭間から本能寺まで/谷口克広 」
ご参考にして下さい。
※次回のくればでの講座は3月12日14時~、「人の記憶 地の記憶 地震伝承を読む」と題し、過去の巨大地震を記録した日記や歴史的影響について歴史の観点からお話しします。
2016年02月15日
ララ洋菓子店・静岡県三島市
とある会合で和菓子が配られた。
何気なしに眺めていたら、ローカルもローカルな名称と、絵柄に引き込まれた。
まだまだ知られていない、ローカルなものがまだまだあるのではないか?
これを見てから、和菓子屋巡りが始まったと言っていい。
洋菓子と比べ、その土地の歴史や風土、産物と、和菓子にはローカルな情報が詰まっている。それでいて、現在の材料を使ったりと、常に革新している。
私は街歩きをする際、和菓子屋をまず尋ねる。和菓子屋には老舗が多く、様々な歳時記に合わせた菓子を作るため、街の様子を見ている。そこには街の様々な情報が詰まっているからだ。
ララ洋菓子店(静岡県三島市広小路町13−2)
三嶋大社ゑびすサブレー

三嶋大社に祀られている事代主命が恵比須神になぞらえられる所からか。
源兵衛川の小舟遊び

かつて、源兵衛川に料理を乗せた小舟を流したという話があります。
湧き水の砂模様

孝行犬の手

市内の円明寺に伝わる話から。
三石神社の時の鐘

本店のすぐ側にある三石神社には宿場街に時を知らせる鐘があります。
親水公園の飛び石

親水公園は色々とありますが、どこなのでしょうか。
三島の里ポテト

小浜池の石ころ

駅前にある公園・楽寿園内の小浜池から。
神池の亀の甲羅

三嶋大社境内に、源頼朝が寄進した池が神池と呼ばれています。亀が居るかは不明。
何気なしに眺めていたら、ローカルもローカルな名称と、絵柄に引き込まれた。
まだまだ知られていない、ローカルなものがまだまだあるのではないか?
これを見てから、和菓子屋巡りが始まったと言っていい。
洋菓子と比べ、その土地の歴史や風土、産物と、和菓子にはローカルな情報が詰まっている。それでいて、現在の材料を使ったりと、常に革新している。
私は街歩きをする際、和菓子屋をまず尋ねる。和菓子屋には老舗が多く、様々な歳時記に合わせた菓子を作るため、街の様子を見ている。そこには街の様々な情報が詰まっているからだ。
ララ洋菓子店(静岡県三島市広小路町13−2)
三嶋大社ゑびすサブレー

三嶋大社に祀られている事代主命が恵比須神になぞらえられる所からか。
源兵衛川の小舟遊び

かつて、源兵衛川に料理を乗せた小舟を流したという話があります。
湧き水の砂模様

孝行犬の手

市内の円明寺に伝わる話から。
三石神社の時の鐘

本店のすぐ側にある三石神社には宿場街に時を知らせる鐘があります。
親水公園の飛び石

親水公園は色々とありますが、どこなのでしょうか。
三島の里ポテト

小浜池の石ころ

駅前にある公園・楽寿園内の小浜池から。
神池の亀の甲羅

三嶋大社境内に、源頼朝が寄進した池が神池と呼ばれています。亀が居るかは不明。
2016年02月13日
本日講演 「海越え、果つる地まで 雄飛と絶望の移民史」 散歩かふぇ ちゃらぽこにて
本日 15時より散歩かふぇ ちゃらぽこにて講演致します。
内容は「海越え、果つる地まで 雄飛と絶望の移民史」です。

(第二次大戦中、アメリカ国内の日系人が強制収容された)
日本が開国を迎え諸外国との交流が始まると、多くの日本人が海外へと渡り懸命に働いた。遠い異国の地で成功を掴んだ者、絶望に打ちひしがれた者、悲喜交々の姿があった。
ハワイ、アメリカ、南米、満州・・・明治以後に国策として進められた移民の歴史を語ります。
「明治時代・開拓・移民・プランテーション・近代史・人口論」に関心がある方にオススメ。
会費:1500円(ドリンク付き)
時間:15時から
開催場所はコチラ・
※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはちゃらぽこさんへ直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
内容は「海越え、果つる地まで 雄飛と絶望の移民史」です。

(第二次大戦中、アメリカ国内の日系人が強制収容された)
日本が開国を迎え諸外国との交流が始まると、多くの日本人が海外へと渡り懸命に働いた。遠い異国の地で成功を掴んだ者、絶望に打ちひしがれた者、悲喜交々の姿があった。
ハワイ、アメリカ、南米、満州・・・明治以後に国策として進められた移民の歴史を語ります。
「明治時代・開拓・移民・プランテーション・近代史・人口論」に関心がある方にオススメ。
会費:1500円(ドリンク付き)
時間:15時から
開催場所はコチラ・
※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはちゃらぽこさんへ直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
2016年02月13日
本日講演 「幕府流転 天下相食む下剋上」 静岡市 くればにて
本日14時より静岡市のシニアライフ支援センター「くれば」にて講演致します。
内容は「幕府流転 天下相食む下剋上」です。

(足利将軍を凌ぐ権力を手にした三好長慶)
室町時代末期、足利将軍の権威は失墜し、将軍ですらそれまでの部下に幕府を追い出される有様であった。それでも力を取り戻そうと、策を巡らし自ら戦場に赴く者も居た。
華々しい戦国大名の活躍の陰で衰退しつつも、戦国時代の鍵を握っていた足利将軍の末期と、「天下人」と呼ばれた者たちの動向を語ります。
「室町時代後期・下剋上・戦国時代・足利将軍に関心がある方におすすめ。」
会費:500円
開催場所はコチラ・静岡市両替町2丁目3-6大原ビル1F シニアライフ支援センター「くれば」
参加は自由です。直接、来場してください。問い合わせはコチラから。054(252)8018
もしくはオーナーメールで直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました
内容は「幕府流転 天下相食む下剋上」です。

(足利将軍を凌ぐ権力を手にした三好長慶)
室町時代末期、足利将軍の権威は失墜し、将軍ですらそれまでの部下に幕府を追い出される有様であった。それでも力を取り戻そうと、策を巡らし自ら戦場に赴く者も居た。
華々しい戦国大名の活躍の陰で衰退しつつも、戦国時代の鍵を握っていた足利将軍の末期と、「天下人」と呼ばれた者たちの動向を語ります。
「室町時代後期・下剋上・戦国時代・足利将軍に関心がある方におすすめ。」
会費:500円
開催場所はコチラ・静岡市両替町2丁目3-6大原ビル1F シニアライフ支援センター「くれば」
参加は自由です。直接、来場してください。問い合わせはコチラから。054(252)8018
もしくはオーナーメールで直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました
2016年02月10日
林檎狩りと渓谷と ③
たまたま階段を下りて来る人が居たので、上まで行けるかと聞くとスグだと聞いたので登ってみることにする。
約200段の階段はかなり急で、みな息も絶え絶え。

岩屋観音

角間渓谷の大小の洞窟は縄文時代の住居跡です。最大の洞窟は岩屋洞窟で、洞窟は横50m、高さ5m、奥行き2~5m、小さいものは縄文時代は住居として利用されていたとされています。

岩屋観音の創建は大同元年(806)、この洞窟を棲家にしていた巨魁・毘邪(ヒヤ)王が鬼達を率いて村人に悪行の限りを尽くしていた。
朝廷は四道将軍である坂上田村麻呂を派遣したが、飛猿のようにすばしっこく、妖術を使い霧に隠れられ、毘邪王を討つことができなかった。
そこで田村麻呂は隣村に安置され霊験が高いと云われる馬頭観音(現在の実相院)に祈願したところ、毘邪王の妖術を封じてようやく討伐できた。田村麻呂は感謝の意とこの地の平穏の為に堂宇を建立し観音像を安置したと伝えられている。観音堂はその洞窟を囲むように建てられ、外側の外壁は建具によって遮られ、内部には小さな仏壇があり観音像と思われる石仏が安置されています。
毘邪王の亡骸は実相院の境内に埋められたと伝えられています。

急な石段を登ったので、皆でお菓子を食べて休憩。

ではもう少し散策してみる。

細い道を行きます。

猿飛岩

眞田十勇士の一人・猿飛佐助が修行に励んだと言われる岩。二つの小さな岩山の間が絶壁となっていて、岩の間を跳んで修行していたという。
その右手に狭い小高い岩があり、そこに立ってみる。

渓谷の奥の山々のが紅葉が展望できました。

他にも見所がありそうなのであるが、ここで日が暮れそうになってきたので、遊歩道を降りる。

親鸞聖人室恵信尼公 療養之地

親鸞上人が越後より京落の途中、奥方の恵信尼が腹痛に倒れたが、角間温泉にて療養し全快された湯として伝えられている。
旅館にてトイレを借りました。

この旅館・岩屋館は古くから角間渓谷に湧出していた鉄泉を源泉として1931年に創業。
農閑期には地元の農家の人も湯治に集まっていたという。
旅館の前に足湯があったので歩いた事もあって足をつけてみたのだが・・・

かなりぬるい。足湯は一般的に温度が高めであるが、このぬるさは足が逆に疲れそうだった。もう夕方なので湯の供給が止まったのか。
山中では日が傾くと一気に暗くなる。

正しく「秘湯」という雰囲気。泊まってみたいです。
ここで関東組とはお別れ。それぞれの帰路につく。
2016年02月09日
2月24日講演 「幕府流転 天下相食む下剋上」 沼津市 高嶋酒造にて
2月24日18時半より講演致します。
内容は「幕府流転 天下相食む下剋上」です。

政変によって京を追われた後も再び将軍に返り咲いた室町幕府10代将軍・足利義植
室町時代末期、足利将軍の権威は失墜し、将軍ですらそれまでの部下に幕府を追い出される有様であった。それでも力を取り戻そうと、策を巡らし自ら戦場に赴く者も居た。
華々しい戦国大名の活躍の陰で衰退しつつも、戦国時代の鍵を握っていた足利将軍の末期と、「天下人」と呼ばれる者たちの動向を語ります。
「室町時代後期・下剋上・戦国時代・足利将軍に関心がある方におすすめ。」
参加費:700円。
開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて
※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)
※自由参加ですが、問い合わせ等は高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
内容は「幕府流転 天下相食む下剋上」です。

政変によって京を追われた後も再び将軍に返り咲いた室町幕府10代将軍・足利義植
室町時代末期、足利将軍の権威は失墜し、将軍ですらそれまでの部下に幕府を追い出される有様であった。それでも力を取り戻そうと、策を巡らし自ら戦場に赴く者も居た。
華々しい戦国大名の活躍の陰で衰退しつつも、戦国時代の鍵を握っていた足利将軍の末期と、「天下人」と呼ばれる者たちの動向を語ります。
「室町時代後期・下剋上・戦国時代・足利将軍に関心がある方におすすめ。」
参加費:700円。
開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて
※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)
※自由参加ですが、問い合わせ等は高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
2016年02月08日
林檎狩りと渓谷と ②
先回の続き…
食事のために上田市街地へ。
上田市はやはり真田氏の地元という事で色々と真田推しである。
城下町風の街づくりのための署名だそうだ。

呉服屋さんですが六文銭と真田グッズが正面に。

自販機も。

そしてサマーウォーズ。これも真田と言えば真田か。

やはり信州という事で蕎麦を。

食事をしつつ、何処を見物しようかと話あいまして、市内に角間渓谷という紅葉の名所があるという事なのでソコに行く事にする。
車で走ること20分ほど。どんどん道が細くなってやや不安感が出てきた所で、目の前に巨大な断崖が迫ってきた光景であった。

一軒だけある温泉宿が良い感じ。
角間渓谷は信濃耶馬溪とも称されるそうだが、確かに似ている。
カメラでは全てを収めきれないのが惜しい。
鬼ヶ城

ここにはかつて鬼が住み、付近の住民に悪さをするので、それを坂上田村麻呂が退治したという。

川も美しい。

丸太の橋を渡ってみる。


この階段の上にも色々と見所がありそうなので、登ってみることにする。

続く…
2016年02月07日
2月6日講演 「二つの天を抱いて 太平は夢の如く」 参考文献一覧
2月6日に三島市のカフェうーるーにて「二つの天を抱いて 太平は夢の如く」についてお話させて頂きました。
参加して下さった皆様、ありがとうございました。
講座に当たっての参考文献は以下の通りです。
書名/著者
後醍醐天皇 南北朝動乱を彩った覇王/森茂暁
足利尊氏と直義 京の夢、鎌倉の夢/峰岸純夫
楠木正成/ 網野善彦
花将軍 北畠顕家/横山高治
新田義貞/峰岸純夫
ご参考にして下さい。
※次回は12月22日18時半から、「日本再起動 室町ルネサンス」と題し、南北朝時代以後の室町時代の経緯と、今に繋がる日本文化への影響についてお話しします
参加して下さった皆様、ありがとうございました。
講座に当たっての参考文献は以下の通りです。
書名/著者
後醍醐天皇 南北朝動乱を彩った覇王/森茂暁
足利尊氏と直義 京の夢、鎌倉の夢/峰岸純夫
楠木正成/ 網野善彦
花将軍 北畠顕家/横山高治
新田義貞/峰岸純夫
ご参考にして下さい。
※次回は12月22日18時半から、「日本再起動 室町ルネサンス」と題し、南北朝時代以後の室町時代の経緯と、今に繋がる日本文化への影響についてお話しします
2016年02月06日
本日講演 「二つの天を抱いて 太平は夢の如く」 三島市 カフェうーるーにて
本日9時半から三島市のカフェうーるーにて行います。
内容は「二つの天を抱いて 太平は夢の如く」です。

(知略と勇猛、誠実な人柄から南北朝双方から称賛された楠木正成)
鎌倉幕府末期、幕府は社会の変化に対応できないまま、各地で倒幕の火が燃え広がり幕府は倒された。
幕府という共通の敵を倒した後、新たな世の中を目指して、新たな形を造ろうとする者、旧来の姿に戻そうと計る者、思惑は巡り朝廷・武家とも親兄弟で相争い、何を信じて良いか判らぬまま、新たな時代が模索された南北朝時代についてお話しします。
「室町幕府・南北朝時代・武家政権・足利尊氏・婆娑羅に関心がある方におすすめ。」
会費:500円+ワンドリンクオーダー
時間:9時半から11時半予定
開催場所はコチラ・カフェうーるー(三島市南本町13-30 ☎055-981-5539)
参加の申し込み不要。
問い合わせはオーナーメール、もしくはうーるーさんへお願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
内容は「二つの天を抱いて 太平は夢の如く」です。

(知略と勇猛、誠実な人柄から南北朝双方から称賛された楠木正成)
鎌倉幕府末期、幕府は社会の変化に対応できないまま、各地で倒幕の火が燃え広がり幕府は倒された。
幕府という共通の敵を倒した後、新たな世の中を目指して、新たな形を造ろうとする者、旧来の姿に戻そうと計る者、思惑は巡り朝廷・武家とも親兄弟で相争い、何を信じて良いか判らぬまま、新たな時代が模索された南北朝時代についてお話しします。
「室町幕府・南北朝時代・武家政権・足利尊氏・婆娑羅に関心がある方におすすめ。」
会費:500円+ワンドリンクオーダー
時間:9時半から11時半予定
開催場所はコチラ・カフェうーるー(三島市南本町13-30 ☎055-981-5539)
参加の申し込み不要。
問い合わせはオーナーメール、もしくはうーるーさんへお願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。




