no">
2014年07月11日
7月10日講演 「幕末世界戦争 革命は火薬の香り」 参考文献一覧
7月10日に三島市のcucurucuにて「幕末世界戦争 革命は火薬の香り」についてお話させて頂きました。
参加して下さった皆様、ありがとうございました。
講座に当たっての参考文献は以下の通りです。
書名/著者
近代日本とイギリス資本/石井寛治
トマス・グラバーの生涯: 大英帝国の周縁にて/マイケルガーデナ・翻訳 村里好俊, 杉浦裕子
アジアの海の大英帝国/横井勝彦
日本経済史(1) 幕末維新期/東京大学出版会
榎本武揚から世界史が見える/臼井隆一郎
ご参考にして下さい。
※次回は8月14日19時から、「大洋を越える運命 音吉・ラナルド・栄之助」と題し、江戸時代後期に漂流に巻き込まれた男・音吉を軸に、互いに影響を与え合うラナルド・マクドナルドと森山栄之助の運命についてお話しします
参加して下さった皆様、ありがとうございました。
講座に当たっての参考文献は以下の通りです。
書名/著者
近代日本とイギリス資本/石井寛治
トマス・グラバーの生涯: 大英帝国の周縁にて/マイケルガーデナ・翻訳 村里好俊, 杉浦裕子
アジアの海の大英帝国/横井勝彦
日本経済史(1) 幕末維新期/東京大学出版会
榎本武揚から世界史が見える/臼井隆一郎
ご参考にして下さい。
※次回は8月14日19時から、「大洋を越える運命 音吉・ラナルド・栄之助」と題し、江戸時代後期に漂流に巻き込まれた男・音吉を軸に、互いに影響を与え合うラナルド・マクドナルドと森山栄之助の運命についてお話しします
2014年07月10日
本日講演 「幕末世界戦争 革命は火薬の香り」 三島 cucurucuにて
本日19時より三島市のcucurucuにて講演致します。
内容は「幕末世界戦争 革命は火薬の香り」です。

19世紀、欧米列強の進出は東アジアに達し、地球規模となった。日本も植民地となるか独立を保てるかの瀬戸際となった。
幕末から明治維新への動乱を、欧米列強の思惑と、暗躍する武器商人たちの視点から見て行きます。
「幕末・19世紀・アジア史・欧米列強・武器商人・戊辰戦争・国家債務問題に関心がある方におすすめ。」
参加費:1000円(ワンドリンク付き)
時間:19時から
※駐車場がありません。公共交通機関(JR三島駅徒歩5分)か近隣の駐車場をお使い下さい。
開催場所はコチラ・cucurucu'
申し込みはオーナーメール、もしくはcucurucu'さんへ直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
内容は「幕末世界戦争 革命は火薬の香り」です。
19世紀、欧米列強の進出は東アジアに達し、地球規模となった。日本も植民地となるか独立を保てるかの瀬戸際となった。
幕末から明治維新への動乱を、欧米列強の思惑と、暗躍する武器商人たちの視点から見て行きます。
「幕末・19世紀・アジア史・欧米列強・武器商人・戊辰戦争・国家債務問題に関心がある方におすすめ。」
参加費:1000円(ワンドリンク付き)
時間:19時から
※駐車場がありません。公共交通機関(JR三島駅徒歩5分)か近隣の駐車場をお使い下さい。
開催場所はコチラ・cucurucu'
申し込みはオーナーメール、もしくはcucurucu'さんへ直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
2014年07月09日
7月19日講演 「オホーツクの霧の海 愛憎の海峡 中編」 散歩かふぇ ちゃらぽこにて
7月19日15時より散歩かふぇ ちゃらぽこにて講演致します。
内容は「オホーツクの霧の海 愛憎の海峡 中編」です。

(千島列島の開拓に向かった千島報效義会)
明治維新を経て近代化した日本と、凍らない港を求めて南下するロシア帝国の利害はやがて衝突し、戦火を交える事になる。
千島・樺太の国境の狭間に生きる日本人と、革命の嵐に翻弄されたロシア人の運命は大きな渦に巻き込まれていく事になる。
明治時代からロシア革命に至るまでの日露関係史を追って行きます。
「ロシア・千島列島開拓・樺太・ロシア革命・大津事件・日露戦争・ポーツマス条約」に関心がある方にオススメです。
会費:1500円(ドリンク付き)
時間:15時から
開催場所はコチラ・
※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはちゃらぽこさんへ直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
内容は「オホーツクの霧の海 愛憎の海峡 中編」です。

(千島列島の開拓に向かった千島報效義会)
明治維新を経て近代化した日本と、凍らない港を求めて南下するロシア帝国の利害はやがて衝突し、戦火を交える事になる。
千島・樺太の国境の狭間に生きる日本人と、革命の嵐に翻弄されたロシア人の運命は大きな渦に巻き込まれていく事になる。
明治時代からロシア革命に至るまでの日露関係史を追って行きます。
「ロシア・千島列島開拓・樺太・ロシア革命・大津事件・日露戦争・ポーツマス条約」に関心がある方にオススメです。
会費:1500円(ドリンク付き)
時間:15時から
開催場所はコチラ・
※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはちゃらぽこさんへ直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
2014年07月08日
車旅、ふたたび ⑦能登町へ
14:55 再スタート 急速に天候が回復。

15:20 古和秀水

總持寺の所有地にある湧き水の古和秀水は、總持寺の開祖・瑩山禅師が龍神より賜ったと伝えられる霊水。「子には清水(しゅうど)、大人には酒になる」という伝説からコワシュウドと名付けられた。
詳しい由来はコチラから
同寺のお茶用の水として大切されて来た。奥能登では唯一、名水百選に選ばれている。
この水を水筒に汲んで、水出し茶を淹れる。


17:10 酒垂神社

拝殿は高台にあるのでやや歩く。
伝承によれば、祭神・大山祇命はアイの風(地元で云う北東方向からの風)で酒樽に乗って漂着したと伝えられている。

高台からの能登町の眺め

神社の向かいにあった銭湯

17:40 真脇遺跡

能登町にある真脇遺跡は、縄文時代前期から晩期にいたる集落跡の遺跡である。
発掘される史料が豊富であるため、「考古学の教科書」などとも呼ばれる。遺跡は1989年に国の史跡に指定され、出土品のうち保存状態の良好なもの219点が1991年国の重要文化財(考古資料)に指定された。

300体を超える大量のイルカの骨から、「日本漁業発祥の地」という碑が建っている。

環状木柱列(ウッドサークル)

円状に並べられたクリ材の半円柱が発掘され、10本の柱で囲んだと思われる直径7.4メートルの環状木柱列。
各々の柱を半分に割り、丸い方を円の内側に向けている。その太さは直径80~96センチもある。

同じ石川県金沢市で先に確認されたチカモリ遺跡の環状木柱列と良く似ており、注目されている。このような巨木を用いた建物や構築物は巨木文化と呼ばれ、日本海沿岸から中央高地にかけていくつか確認されている
18:00 再スタート やや燃料が少ないのが不安な走行。
18:25 見付島

空海が佐渡島からやってきて最初に見つけたことから「見附島」と命名されたとする地名伝承がある。
島は長さ約150m、幅約50m、標高約30mの小島で、全体が珠洲市の特産物である七輪の原材料として知られる珪藻土で出来ており、珠洲をあらわす象徴であると共に能登半島国定公園の景勝地として知られ、また正面からは人の顔のようにも見えることから多くの観光客を集める。
1991年の平成3年台風第19号、1993年の能登半島沖地震、2007年の能登半島地震、新潟県中越沖地震などの自然災害による崩落と、経年による風化のために少しずつ形が変わっている。

その姿から軍艦島とも呼ばれる。
19:15 給油 16.1ℓ
19:20 道の駅 すずなり 本日終了 307km走行
2014年07月07日
7月6日teshio講演 「巨大国策 捕鯨産業」 参考文献
7月6日、沼津市のteshioにて「巨大国策 捕鯨産業」についてお話させて頂きました。
お越し下さった皆さん、ありがとうございました。
講座に当たっての参考文献は以下の通りです。
書名/著者
「捕鯨Ⅰ・Ⅱ/山下渉登 」
「南氷洋の捕鯨/山田致知」
「鯨取り絵物語/中園成生 安永浩」
「クジラは誰のものか/秋道智彌」
「よくわかるクジラ論争/小松正之」
ご参考にしてください。
※次回のteshioでの講座は8月10日14時からです。
お越し下さった皆さん、ありがとうございました。
講座に当たっての参考文献は以下の通りです。
書名/著者
「捕鯨Ⅰ・Ⅱ/山下渉登 」
「南氷洋の捕鯨/山田致知」
「鯨取り絵物語/中園成生 安永浩」
「クジラは誰のものか/秋道智彌」
「よくわかるクジラ論争/小松正之」
ご参考にしてください。
※次回のteshioでの講座は8月10日14時からです。
2014年07月06日
本日講演 「巨大国策 捕鯨産業」 沼津市 teshioにて
本日14時より沼津市のカフェteshioにて講演致します。
内容は「巨大国策 捕鯨産業 」です。

(鯨から採取された油の樽が並ぶ港)
対立する捕鯨に関しての考え方。欧米各国が捕鯨を推進していた時代、鯨を巡って繰り広げられた欧米各国の思惑が世界史にも影響を与えた背景と、日本の古式捕鯨とは異なる視点についてお話しします。
「捕鯨問題・環境問題・産業史・動物保護・」に関心がある方にオススメ。
会費:500円
※飲食店ですので1人1オーダーのご協力をお願い致します。
時間:14時から(前回までと時間が異なります)
※お車でお越しの方は2人以上の相乗りで文化センターの駐車場をご利用頂くと、1時間無料になります。
開催場所はコチラ・沼津市民文化センター内のカフェ・teshioにて
申し込みはオーナーメール、もしくは「info★cafe-teshio.com」(★を@に変更してメールを)で直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました
内容は「巨大国策 捕鯨産業 」です。

(鯨から採取された油の樽が並ぶ港)
対立する捕鯨に関しての考え方。欧米各国が捕鯨を推進していた時代、鯨を巡って繰り広げられた欧米各国の思惑が世界史にも影響を与えた背景と、日本の古式捕鯨とは異なる視点についてお話しします。
「捕鯨問題・環境問題・産業史・動物保護・」に関心がある方にオススメ。
会費:500円
※飲食店ですので1人1オーダーのご協力をお願い致します。
時間:14時から(前回までと時間が異なります)
※お車でお越しの方は2人以上の相乗りで文化センターの駐車場をご利用頂くと、1時間無料になります。
開催場所はコチラ・沼津市民文化センター内のカフェ・teshioにて
申し込みはオーナーメール、もしくは「info★cafe-teshio.com」(★を@に変更してメールを)で直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました
2014年07月05日
車旅、ふたたび ⑥能登半島へ
4:30起床

寝場所は小矢部市内の某所にて
5:15スタート
国道8号線を西へ向かい、石川県かほく市にて国道159号線に入り能登半島方面へ。
6:30給油 9ℓ
志賀町の国道沿いにて

小雨交じりだったので立ち寄りはしなかったが、旅行情報の「じゃらん」によると、
「全長460.9メートルのとても長いベンチ。 「日本海に沈む夕日を見てほしい」そんな地元住民の思いを受けて、1987(昭和62)年に延べ830人のボランティアの手で組み当てられ、1989(平成元)年には世界一長いベンチとしてギネスブックに掲載された。 ベンチ付近は「サンセットヒルイン増穂」と呼ばれ、夕日の名所となっている。 」
7:00輪島市黒島地区
黒島地区の入り口にあった北前船の模型

黒島地区は江戸時代に幕府の天領となり、北前船の船主、船頭の居住地として江戸時代後期から明治時代中期かけて栄えた。国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。
黒島地区の町並みは、切妻屋根平入が基本であり、総じて下見板張りの板壁に、屋根には表面に釉薬を塗った光沢のある黒瓦が乗っている。

16世紀後期、室町時代の末期には番匠屋善右衛門が黒島で始めて廻船業を起こし、加賀一向一揆の兵糧米を運んでいたという。以降、数多くの船問屋が創業し栄えていった。特に森岡屋は總持寺の御用船として使われていた船問屋であった。なお、廻船業が盛んであったとはいえ黒島に北前船を留める港は無く、この集落は船主や船頭、水夫などといった廻船業者が住居する集落として発展したものである。
江戸時代に入った17世紀初頭、黒島集落はかなりの規模に発展していた。17世紀後期の天和4(1684)年には能登国内62ヶ所の集落が幕府の直轄地、いわゆる天領として治められるようになったのだが、黒島地区はその能登天領集落の中で最も規模の大きい集落であり、黒島の廻船業もまた能登外浦で最も発達していた。
石川県指定有形文化財 角海家住宅

七艘の北前船を所有、廻船問屋として活躍し栄華を誇った角海家の収蔵品を展示している。
黒島地区は明治前期には500戸を超えていたという。しかし明治中期になると全国に鉄道が張り巡らされ、運輸の主軸は海上から陸上へと移り変わり、北前船は衰退して廻船業の需要は減少の一途を遂げた。角海家もこの頃に廃業した。
廻船業が廃れた後、黒島の人々は漁業で生計を立て暮らして行き、昭和になると外洋船の船乗りとして活躍したという。
海からの風を防ぐための竹柵をよく見る。




7:35 雨により中断
続く…
2014年07月04日
7月13日講演 「巨大国策 捕鯨産業」 静岡市くればにて
7月13日14時より静岡市のシニアライフ支援センター「くれば」にて講演致します。
内容は「巨大国策 捕鯨産業 」です。

(北極海で行われていた捕鯨)
対立する捕鯨に関しての考え方。欧米各国が捕鯨を推進していた時代、鯨を巡って繰り広げられた欧米各国の思惑が世界史にも影響を与えた背景と、日本の古式捕鯨とは異なる視点についてお話しします。
「捕鯨問題・環境問題・産業史・国際政治」に関心がある方にオススメ。
会費:500円(+ワンオーダーをお願いします)。
開催場所はコチラ・静岡市両替町2丁目3-6大原ビル1F シニアライフ支援センター「くれば」
申し込みはコチラから。054(252)8018
もしくはオーナーメールで直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました
内容は「巨大国策 捕鯨産業 」です。

(北極海で行われていた捕鯨)
対立する捕鯨に関しての考え方。欧米各国が捕鯨を推進していた時代、鯨を巡って繰り広げられた欧米各国の思惑が世界史にも影響を与えた背景と、日本の古式捕鯨とは異なる視点についてお話しします。
「捕鯨問題・環境問題・産業史・国際政治」に関心がある方にオススメ。
会費:500円(+ワンオーダーをお願いします)。
開催場所はコチラ・静岡市両替町2丁目3-6大原ビル1F シニアライフ支援センター「くれば」
申し込みはコチラから。054(252)8018
もしくはオーナーメールで直接お願いします。
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました
2014年07月03日
車旅、ふたたび ⑤駆け抜けて、富山
先回の続き…。
諏訪大社下社秋宮から再び走り出す。
塩尻峠を越えると国道の終点表示が。

他の国道でこういう表示はあるのでしょうか
この先、松本から国道158号線で西へ向かう。北アルプスの麓、渓谷とトンネル地帯を走り続けて岐阜県に。
471号線、41号線を走り続けたので写真は無し。
その途中、鉱山で栄えた神岡にて撮影。
現在は神岡町ではなく合併により飛騨市となっている。
そして、富山へ抜ける。
通り掛かった射水市串田地区の櫛田神社

式内社である。

近くには縄文時代の遺跡も。
境内には不似合いなコンクリート建築は大伴二三彌ステンドグラス記念館

大伴二三彌氏は射水市出身。亡くなる直前、作品約三百点を射水市に寄贈し、「森に囲まれた櫛田神社の地に展示してほしい 」との意を受け、甥が宮司を務める櫛田神社に記念館を建設したもの。
入場無料だそうだが、来た時間が遅かったゆえ、入れなかったのが残念。
小矢部市に在ったカレーのお店・Jinjin。

喫茶店のような雰囲気で、年配の夫婦で切り盛りされている。他にも三組ほどの客が。
幟の「焼きカレー」が目について入ったのだが、「マダムチキンカレー」というのが気になったので注文。
小矢部市は養鶏が盛んな所で、鶏のブランド化を図った「おやべ火ね鶏」があり、「ひねたとり」を「マダム」としたそうだ。
このお店でスーパーを聞いて買物。その後で、雨が予想されるので、雨を避けられる所を求めて寝場所を探して終了。
続く…。
2014年07月02日
7月1日講演「天駆ける山伏たち 山と里を結ぶ道」について参考文献
7月1日、沼津市のLot.nにて「天駆ける山伏たち 山と里を結ぶ道」についてお話させて頂きました。
お越し下さった皆さん、ありがとうございました。
講座に当たっての参考文献は以下の通りです。
書名/著者
「山伏入門/宮地泰年」
「図説 役小角/」
「熊野 異界への旅/山本殖生」
「山岳修験の招待/」
ご参考にしてください。
※次回は8月5日18時半から「海賊たち 境界を超える人々」と題し、歴史の転換点に現れる海賊という集団を通じて、海からの視点をお話しします。
お越し下さった皆さん、ありがとうございました。
講座に当たっての参考文献は以下の通りです。
書名/著者
「山伏入門/宮地泰年」
「図説 役小角/」
「熊野 異界への旅/山本殖生」
「山岳修験の招待/」
ご参考にしてください。
※次回は8月5日18時半から「海賊たち 境界を超える人々」と題し、歴史の転換点に現れる海賊という集団を通じて、海からの視点をお話しします。
2014年07月01日
本日講演 「天駆ける山伏たち 山と里を結ぶ道」 沼津市 Lot.nにて
本日18時半から沼津市のLot.nにて行います。
内容は「天駆ける山伏たち 山と里を結ぶ道」です。
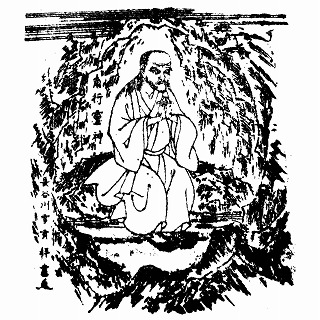
(富士講の開祖・角行)
山伏と言われた山岳修験者たち。歴史の表舞台に現れる事は少ないが、明治時代までの庶民たちに与えた影響は少なくない。
余り馴染みが無い修験道の実態と、民衆に与えた文化的な影響についてお話します。
会費:1000円(ドリンク付き)
時間:18時半から
開催場所はコチラ・沼津市上土町60 岡田ビル1F(元Floyd沼津店 店舗)


※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接お願いします。
 055-919-1060
055-919-1060
ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。
内容は「天駆ける山伏たち 山と里を結ぶ道」です。
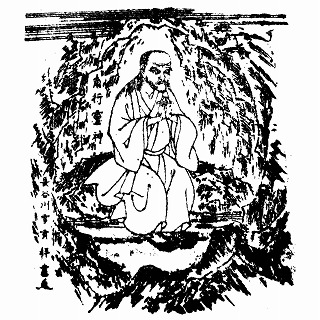
(富士講の開祖・角行)
山伏と言われた山岳修験者たち。歴史の表舞台に現れる事は少ないが、明治時代までの庶民たちに与えた影響は少なくない。
余り馴染みが無い修験道の実態と、民衆に与えた文化的な影響についてお話します。
会費:1000円(ドリンク付き)
時間:18時半から
開催場所はコチラ・沼津市上土町60 岡田ビル1F(元Floyd沼津店 店舗)


※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。
申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接お願いします。
 055-919-1060
055-919-1060ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。
本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。




