no">
2011年08月08日
被災地へ向かう 完全版 4月8日 ボランティア初日
5時半起床

昨夜の地震でその直後は停電していたが、一晩明けてどうやら復旧したようだ。公園のトイレに入ったら、便座が暖かい。
テント場に居る人と色々とボランティアに関しての話を聞く。
8:45ボランティア受付

総勢50人ほど、私の班は私以外は男性3人、地元の女子大生4人だが高校時代のジャージを来ている。
今まで津波の被害というものが想像出来なかったが、伺った家に近づくにつれ、報道で見た映像が眼前に展開された。

伺った家は老夫婦の家で聞く所、1mほどの津波に呑まれたという事で壁に線で記されていた。
作業は津波によって流されてきた藁の除去。それほど力仕事で無いが、一様に藁が積もり、二時間の作業で2m程の山になった。

午前の作業が終わり昼食。午後の受付に向かうと、午後の作業は依頼が少ないので作業は無し。ただ、道具の洗浄を頼まれ行った。それも一時間ほどで終了した。
隣のテントの人に車に乗せてもらい街の案内をしていただいた。日帰り入浴出来るビジネスホテルを教えて貰ったが、昨夜の地震で給湯設備が壊れてしまい使えないという。
竹駒稲荷について聞かれたので、過去二回行った事を言うと案内する事に。

社殿や随神門は無事だが、燈籠がことごとく倒れていた。
その人は翌日に帰るので、テント場にいる人で軽く宴会する事に。他のテントの人も加わり自己紹介。北海道の利尻島に住んでいる人、横須賀の介護施設から派遣されて、足湯ボランティアを展開してるお二人、世話になった人は東京でシステムエンジニアを自営でやっている人である。
こうして夜は更けていった。
昨夜の地震でその直後は停電していたが、一晩明けてどうやら復旧したようだ。公園のトイレに入ったら、便座が暖かい。
テント場に居る人と色々とボランティアに関しての話を聞く。
8:45ボランティア受付
総勢50人ほど、私の班は私以外は男性3人、地元の女子大生4人だが高校時代のジャージを来ている。
今まで津波の被害というものが想像出来なかったが、伺った家に近づくにつれ、報道で見た映像が眼前に展開された。
伺った家は老夫婦の家で聞く所、1mほどの津波に呑まれたという事で壁に線で記されていた。
作業は津波によって流されてきた藁の除去。それほど力仕事で無いが、一様に藁が積もり、二時間の作業で2m程の山になった。
午前の作業が終わり昼食。午後の受付に向かうと、午後の作業は依頼が少ないので作業は無し。ただ、道具の洗浄を頼まれ行った。それも一時間ほどで終了した。
隣のテントの人に車に乗せてもらい街の案内をしていただいた。日帰り入浴出来るビジネスホテルを教えて貰ったが、昨夜の地震で給湯設備が壊れてしまい使えないという。
竹駒稲荷について聞かれたので、過去二回行った事を言うと案内する事に。
社殿や随神門は無事だが、燈籠がことごとく倒れていた。
その人は翌日に帰るので、テント場にいる人で軽く宴会する事に。他のテントの人も加わり自己紹介。北海道の利尻島に住んでいる人、横須賀の介護施設から派遣されて、足湯ボランティアを展開してるお二人、世話になった人は東京でシステムエンジニアを自営でやっている人である。
こうして夜は更けていった。
2011年08月06日
被災地へ向かう 完全版 4月7日 現地入り
 1419新庄発
1419新庄発東根市辺りからは雪が見当たらない。
天童ではくちびる美人コンテストというのをやっているらしい。
 1527山形着
1527山形着山形駅前のバスターミナル
今まで、様々なボランティアセンターに電話をしていたが繋がらなかった。
山形駅に着いて始めて岩沼市のボランティアセンターに繋がり現地の状況を聴く事が出来た。「県外の人」「個人」「テント設営できる」という私の三点の条件を満たしているのは現段階で岩沼市だけなので、岩沼市に向かう事にする。
道行く山形の小学生は詰襟制服が多い。
 1559バス乗車 900円
1559バス乗車 900円
高速道路に入り宮城県境を越えると、それまでとは打って変わって緊張感が全身に走った気がした。
しかしバスで走っていても、それほどの被害が感じられない。
バスは仙台市に入る。見た所、仙台市街内は目立った被害見られず。
 1710仙台駅
1710仙台駅
駅の外壁は全て補修のようである。
現地入りの前に近くのスーパーで買い物、見た所物資は豊富である。

むしろ、地元よりも多いかもしれない。優先的に物資が融通されていたのだろうか。
駅前の中心地には震災の写真を展示してあった。

しかし足を止めて見る人は余り居なかった。
岩沼市に入る前、駅員の人に岩沼市に入るための交通手段を聞いた。自分の知る限り、まだ東北本線は復旧してなかったのだ。だからこそ、山形を経由して来た訳で。
すると、「東北本線乗れば」との声。なんとこの日に復旧したという。東北本線なら一日で来れたのだが…。とも思うがこれで首尾よく岩沼市に入る。
 1815あおば通り駅〜1818仙台東北本線1839〜1900岩沼駅
1815あおば通り駅〜1818仙台東北本線1839〜1900岩沼駅岩沼市を下車すると、各地へ向かうバスがひっきりなしに動いている。東北本線は復旧したが、常磐線方面は海岸に近いのでまだ復旧が出来ていなかった。
駅前の案内図でテント場を確認し、暗い中を歩いて行った。すると途中で国道4号線があるのだが、道沿いの吉野家が営業していた。食料を3日分ほど用意していたので拍子抜けしてしまった。でもちょうど夕食をこの吉野家で済ませ、公園の場所を聞いておいた。
1950テント場の中央公園に着。見た所、二組のテントがある。早速テント設営に入る。
2035終了し、そのまま就寝に入る。
眠って一時、なにやら揺れ始めた。まあ、余震もあろうとは思ってそのまま寝ころんでいたが、揺れが止まらずどんどん大きくなる。ラジオを点けたが、ヘンな音がするばかりである。
2332地震発生、テントで周辺は倒れる物もないので冷静だったが、建物でないのにガタガタと音がするのが不思議だった。
二分ほどして揺れが収まり、周りの住宅に電気がつくが一斉に消え真っ暗に。サイレンが鳴り響き避難する車の渋滞も。しかし信号が消えているので国道4号線を渡れない。ヘルメット被らずバイクで避難する人も。
テント場に居る人同士で集まる事になり、此処は前の地震でも津波は来ていないとの事を聞きひと安心。それが顔合わせになった。
現地入り初日、大地は手荒い歓迎を用意した。
続く…。
2011年07月30日
被災地へ向かう 完全版 4月7日 新庄市散策
 1250新庄駅着
1250新庄駅着駅舎内に飾ってあった新庄祭りの山車。

250年の伝統があるとか。
駅舎から通りを望む。

駅舎遠望

新庄駅は山形新幹線の終着駅。従って駅舎も新しくなったのであろうが、他の駅に比べて人が少ない気がする。と、言うか居たのは女子高生一人だけ。
新幹線が通じたはいいが、それに伴い元々の在来線は本数が少なくなり不便になり益々利用者が減るという例の一つを如実に表している。
新庄駅すぐ脇にある煉瓦の機関庫。

現在も現役で使用されている。近代化遺産に指定。
商店街を歩いていると、至る所で雪解け水が流れていてどうも足元が落ち着かない。アーケードの屋根からもばしゃばしゃと落ちてきていたりする。
新庄市の中央通りは「こぶとりじいさんとおり」となっている。。
他にも民話にちなんだ名前があるようだ。
最上公園。最上という名から最上氏かと思ったら、新庄城を築いたのは戸沢氏。

公園内は雪置き場になっているのか、周辺より一際雪が堆くなっていた。
図書館があったので、新庄の郷土資料などに目を通して見る。
そろそろ駅に戻る事にする。
続く…。
2011年07月27日
被災地へ向かう 完全版 4月7日 酒田から陸羽西線へ
弁当屋があったので弁当を購入し、市役所のベンチで食事。
市役所前にある旧鐙屋

酒田を代表する廻船問屋だったとか。
酒田駅に戻る。
途中で和菓子を購入。
 1145陸羽西線乗車
1145陸羽西線乗車
車内で友達が皆都会に出て寂しいという女子二人がしんみりしていた。これも地方の一面であろう。
狩川駅から風力発電を見る

最上川の流れ

心地よい揺れと雄大な景色に何時しか眠りに入って行った…。
続く…。
2011年07月24日
被災地へ向かう 完全版 4月7日 酒田港の山居倉庫
本間家の旧宅を見た後、その本間家の富の元になった庄内米の山居倉庫へ。
山居倉庫は最上川河口の酒田港に面している。


山居倉庫は明治26年(1893)、酒田米穀取引所の付属倉庫として建造され、築百年以上経った今も現役の農業倉庫として活躍している。


見ていたら実際に米の搬入や搬出が行われていた。

小鵜飼船という最上川の舟運に利用された小舟。

土蔵造りの12棟の屋根は二重構造で、倉の内部は湿気防止構造になっているほか、背後を囲むケヤキの大木は日よけ、風よけの役目を果たし、自然を利用した低温管理が行われている。


倉庫の裏のケヤキ並木が非常に趣深い所だったが、表に出ると観光施設になっている面もあって大型の観光バスが並んでいて、何か現実に戻された気分だった。
続く…。
2011年07月19日
被災地へ向かう 完全版 4月7日 酒田の本間家
酒田は北前船の交易で栄えた港町。もっとも栄えたのは本間家である。
「本間様には及びはせぬが、せめてなりたや殿様に・・・・」
という歌にも詠まれたほどに栄え、三井・住友にも劣らなかった。(詳しくはコチラ)
日本一の大地主であったが、起業に熱心では無く、明治以後は一地方企業に留まった。
本間家旧宅



本間家旧宅の向かいにある「お店」という商売を営んでいた建物。

続く…。
2011年07月17日
被災地へ向かう 完全版 4月7日 日本海を望む2
越後寒川駅の先に「鉄道塩害研究所」なるモノを発見。
どうやら鉄道に使う資材を吹き晒しにしてその痛みを試験しているようだ。
板塀の家屋が多い
少し寝る
山形に入ると再び雪が多い。鶴岡からは月山が真っ白



 0930酒田
0930酒田酒田駅にあった獅子頭

酒田駅全容。

さて、ここから酒田市内を散策する。
続く…。
2011年07月15日
被災地へ向かう 完全版 4月7日 日本海を望む
0535起床
周辺を散策してみるが、商店などは無いようだ。
駅寝した加治駅

 0657加治駅乗車
0657加治駅乗車
平木田駅周辺は海側に防風林、風がキツいのであろう。

延々と平野である

坂町駅での高校生は挨拶が良い、ここから米沢方面に向かうのでも良かったが、せっかくなので日本海を見てみたいと思った。
岩船駅辺りからは堆肥の香りが車内まで
村上駅で大半下車、そのさき日本海を見る。
越後早川からは粟島と断崖絶壁

桑川駅は昔、旅をしていた時に野宿した「道の駅笹川流れ」に隣接していたのに驚き。
三角形の待合室と今川駅、という駅名が気になる。

周辺を散策してみるが、商店などは無いようだ。
駅寝した加治駅

 0657加治駅乗車
0657加治駅乗車平木田駅周辺は海側に防風林、風がキツいのであろう。

延々と平野である

坂町駅での高校生は挨拶が良い、ここから米沢方面に向かうのでも良かったが、せっかくなので日本海を見てみたいと思った。
岩船駅辺りからは堆肥の香りが車内まで
村上駅で大半下車、そのさき日本海を見る。
越後早川からは粟島と断崖絶壁

桑川駅は昔、旅をしていた時に野宿した「道の駅笹川流れ」に隣接していたのに驚き。
三角形の待合室と今川駅、という駅名が気になる。

続く…。
2011年06月28日
被災地へ向かう 完全版 雪国
民俗資料館を出て温泉街散策、夕暮れにアーク?彩雲?を見る。
 1743再び乗車
1743再び乗車水上駅の次の湯檜曾駅から土合駅の間はトンネル駅。何かブレードランナーの音楽が頭に流れた。
ゴツゴツ振動が来る、ループしているらしいがトンネルなのでよくわからない、すごいスピード。
トンネルを抜けると雪国だった。確かにこれほどの景色の一変はそうそう得られない所だ。。
スキー場ですが、使われなくなった車両を使って雪止めにしているようだ。
その手前にも雪は有ったが量が違う。
越後湯沢で真っ暗に。
新潟の人の会話は訛りが感じられない
1935小出駅の先で車両故障によりバスにて振替輸送にこんな事は初めて。
2001バス発車2105長岡
長岡駅周辺は居酒屋ばかりで食事出来る所が無い。
2155信越本線〜2255新津2301羽越本線は機関車、羽越本線〜2334新発田2352〜2358加治・終了、駅で寝る事にする。
こうして一日目が終わった。
2011年06月23日
被災地へ向かう 完全版 水上町歴史民俗資料館
「水上町歴史民俗資料館」という標識を見かけ、時間もあるので入ってみる事にする。
資料館手前にある国指定の重要文化財である戸部家住宅。

軒先が雪の重みに耐えられるような重厚さを持っています。

雪靴

雪深い所ならではで、なかなか興味深い。
坂東館と言う芝居小屋があった時の株券。

このように、お仕着せの「文化センター」ではなくかつては地元の人達が文化を担っていたのです。
この地方で採れる一の沢砥石。全国へ出荷されたという。
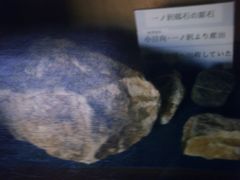
全体的に雪深い山村での生活と、かつて交通の主役であった馬の道具を色々と見る事が出来たのは興味深かった。
ただ、清水トンネル工事や、ダム建設についてももう少し知りたかった。
資料館に「富士浅間神社」と書かれたお札があったので、資料館の人に場所を聞いてみたが、歩きでは行けない所なので残念。あとは三峰神社のお札も良く見かけた。
ここで地元の神様の名を聞けたのが何となく心強かった。
図書室では地元の郷土史の本を眺めてみる。
続く…。
2011年06月22日
被災地へ向かう 完全版 水上温泉2
次第に温泉場に入って行く。
子供の頃にCMでよく見た「ホテル聚楽」が。
こんなポスターが。
ダムカレーが!
温泉街を歩いていると、「水上民俗資料館」と書いてあったのでそこに入ってみる事にする。
続く…。
2011年06月20日
被災地へ向かう 完全版 上越線の車窓から
 13:31高崎駅にて上越線に乗り換え。
13:31高崎駅にて上越線に乗り換え。目の前のカップル、アニメ声の女子に様々なポイントカードを見せて自慢する男。だがSuicaを知らないらしい。
車窓からは赤城山が見える。思い出の地です。
津久田駅から岩本駅間は何度も利根川を渡る。そして雄大な屏風岩。
どういった経緯でこんな地形が生まれたか気になります。
岩本駅に見える発電所。
次第に谷川岳の雄大さが近付いてくる
続く…。




